参政党が夏の参院選(2025 年 7 月)で躍進したことをきっかけに、もちろん、私は参政党に対し明確に異議を有しているのですが、なぜこのようなことが起きているのか、現状をどのように捉えていいのか、を整理するために、そして自らの漠とした不安を少しでも解消するために、識者の言説を集めていました。
いくつかみるなかで、これは理路整然としていて、いくらか「隠れた構造」も説明してくれているな、と思えたのが、日本思想を専門にしている先崎彰容です。
先崎彰容による、参政党の分析
例えば、「日本とは何か?西郷隆盛、本居宣長、福澤諭吉の日本論」 (※1)では、先崎は、昨今の NHK 党であったり、参政党であったりという現象を、反近代であると評じています。これは、ロシアのウクライナ侵攻であるとか、中国の昨今の動向、そしてトランプ現象とも共通していて、要するに第一次世界大戦以降、アメリカ覇権型の世界観だったのだが、それとは別の在り方の価値観を示す現象。ロシアや中国が、アメリカ覇権型の世界観へのオルタナティブの表明であるというのは理解できるのですが、ではトランプは何なのかというと、トランプにとっての近代とは、民主党。
以上が先崎の考えで、ここからは私の推察なのですがが、そこで、参政党が、保守的な側面を持ち、アンチ・グローバリズムも主張しているのにも関わらず、国会で「トランプ政権を参考にしないのか」と質疑したのは(※2)、反近代という点でトランプと共感しているからでしょう。私自身も、近代は乗り越えられなければならないと思うのですが、しかしロシア、中国、トランプ、そして日本で言えば参政党の方法というのは、近代を乗り越えるどころか前近代であり、かつ野蛮、つまり何ら平和的手段でないという点で、到底受け入れられるものではありません。
選挙マーケティング
で、参政党が躍進したのは、やはり主張の表現のキャッチーさにあった、自覚的なのかどうかは分からないけどある意味マーケ的な成功だったのだ、と私は思っているのだけど(その点で、私は、白井聡の意見に賛同)、だってリベラルの顔が野田元総理で、のっそりのっそり正論を話しても、誰にも刺さらないだろうから。
なので、リベラルである私にとっては、左派は左派でキャッチーさが必要なのですが、今回の参院選きっかけで左派における「キャッチー」の中心に躍り出た(と私は持っているのですが、)のが春ねむりで、たしかに音楽はカッコいいのですが、いかんせんハードコア臭がキツい。
SEALDs をもう一度
キャッチーな左派として一定、成功を収めたのは、近年(とは言えもう 10 年も経ってしまったのだが)で言えば SEALDs で、正直、当時は私も、冷笑的な視線を向けていたのだが、今となっては、もっと真剣に支持するべきだった、あの運動が(たとえ母体が解散したとしても)継続的になるように、左派の主張をキャッチーな表現を、もっと真剣に考えるべきだった、と今となっては思います。SEALDs は解散してしまったようですが、以降、メンバーはどのような政治的コミットメントをしているのだろうか、と検索したら、「デモで社会は変わる?人に刺さる発信とは?リベラルなぜ弱体化?牛田悦正&宇佐美典也&中川淳一郎と議論」 を見つけました。正直、内容的にはヒドいものでしたが、牛田悦正の理想を追い求める主張に、私は十分な理解を示したいと思いました。し、彼のような意見に私は肩入れしたいですね。
安野貴博の危険さ
先崎の出演している動画に話を戻すと、安野貴博と議論する動画も見ました( 【対論 安野貴博&先﨑彰容】AIエンジニアが変える日本政治 2025/7/30放送)。私は安野には懐疑的で、というのも、安野が目指すデジタル社会って、それって高度管理社会で、割とディストピアにしか思えないから。というのも、テクノロジー自体は中立なので(おそらく)、それをよく使うこともできるし、悪く使うこともできる。なので、権力監視装置としてデジタルを活用できるということは、同じ技術を大衆監視装置としても使える、ということだから。たとえば全てデジタル通貨にして、個人の経済活動を把握し、そこから税金などの計算を容易にできるようになる、みたいな社会が実装されると、経済活動という一個人のプライバシーに関わる行為が完全な監視下に置かれてしまいますよね。それって望ましいですか? というのは、一つ、疑義を呈したいですね。
安野貴博は自身の政治思想を確立するべき
安野によれば既存の政治思想(典型的な右派・左派)では捉えきればい政治的な軸が現れてきていて、自身の政治的立場も既存の政治思想では捉えきれない、と主張していますが、そうであっても安野には、一度、もし既存の政治思想であればもっとも立場的に近いのはコレ、というのをしっかり示すべきですね。でないと国民にとって不利益なデジタル活用を、権力者が推進した場合、それは無惨な結果になってしまうから。この点について、先崎ははっきり「デジタル民主主義」なる概念に否定を突き付けていて、先崎は信頼できる学者かもな、と思った。
一方で、先崎は安野の本質をまだ見抜けていないのでは? と思う点もあり、というのも、安野は「スタートアップはレッドオーシャンだから、政治家に転向した」というのがおおよその私の見立てであり(※3 )、決して政治そのものに関心があるのではなく、うまく戦略的に選挙に出れば、当選するし、メシのタネになる、くらいに考えているだろうから。 要するにいわゆる to G の、補助金ビジネスの究極形であり、安野にとっては選挙戦略というのは国会議員の給料をゲットするための事業戦略なのだろう、と思う。この点に本人がどれだけ自覚的なのかは不明だが、「政治はブルーオーシャン」とか言ってしまっている時点で、少なくともそういった片鱗はあると言わざるを得ません。なので安野は、先崎の思うような「政治の季節」の再来のような人物ではなく、ビジネスの延長線上としての政治。そういう点で、昨今の新興政党(NHK 党、参政党)と同様のカテゴリーとも言えますね。
※1 この動画で驚かされたのは、佐々木紀彦はわりとしっかりとした、ハードな読書家だ、ということ。
※2 参政党・神谷宗幣代表「トランプ大統領と一緒にやろうと提案しては」 首相に迫ったあんな政策、こんな政策 https://www.tokyo-np.co.jp/article/426461
※3 【メディアが報道しない真実】経営者から政治家へ。安野たかひろが”初選挙で15万票”を獲得できた本当の理由とは? https://youtu.be/xtdiqMN1EMc?si=-jHWOLh6l_zL5jnN


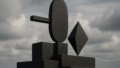
コメント